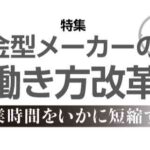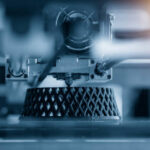前号では、日本金型工業厚生年金基金の制度移行に伴い、年金を退職金化することで得られるメリットなどを紹介した。では、そうした場合に加入者にはどの程度の負担や効果があるのか。より分かりやすく解説するために、モデルケースをも…
記者の目 ‐Reporter`s eye‐
今回の“コロナ禍”で見えてきたのは、変化の必要性だ。受注や生産活動が制限される中、デデジタル化やITツールの活用など以前から指摘されていた課題が改めて浮き彫りになった。都内のある金型メーカーは、「変革の契機となるのは間違いない」と話す。
業務体制だけでなく、重要構造の変化に伴うサプライチェーンの見直しなど、この先業界を取り巻く環境も大きく変わるとみられる。金型メーカー各社には、感染拡大を防ぎ、従業員の安全確保に取り組むと同時に、感染が収束した“アフターコロナ”の世界をどう描くかが問われている。
金型新聞 2020年4月10日
関連記事
自動化と人材育成—。自動車産業に関わらず、あらゆる製造現場において共通の課題となっている。人手不足は深刻化しており、課題解消に自動化、省力化は欠かせない。いかに若手に技能を伝承していくかも喫緊の課題となっている。一方で、…
大型金型の需要に対応 プラスチック金型を手掛ける黒田製作所(岐阜県羽島郡岐南町、058・247・7423)は自動車向けの大型プラスチック金型に対応するため、本社そばに新工場を立ち上げ、UBEマシナリーの大型射出成形機「3…
課題多き働き方改革 働き方改革関連法案の施行から4年。金型業界でも労働時間短縮や生産性の向上など、働き方改革は進んでいるのか。現状を調べるため、本紙ではアンケートを実施した。調査からは、改革には前向きに取り組んでいるもの…
平面研削加工はこれまで、加工条件の設定や砥石の管理に高い技能が必要なため熟練技能者の存在が不可欠だった。しかし近年、自動化技術をはじめとする様々な機能を搭載する平面研削盤の登場で、誰でも簡単に加工できるようになりつつある…