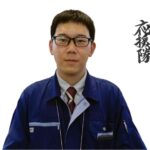アイユーキ技研は金型のロック、アンロック動作を安定して確実に行えるよう、機械式のプラスチック金型用の型開き制御装置を自社開発した。 従来のアンロック動作はスプリングに頼っており、スプリングが戻らずに爪部分が引っ掛かり、ア…
金型企業の代弁者として情報を発信
日本金型工業会 小出 悟 会長に聞く
人材の不足や育成、CASE(コネクティビティ・オートノマス・シェアード・エレクトリック)に代表される自動車産業の変化による影響、台頭する新興国など、日本の金型産業は様々な課題を抱えている。これらに対してどう立ち向かっていくか。新しく日本金型工業会の会長に就任した小出悟氏(小出製作所社長)に業界団体として取り組むべきことや今後の方向性などを聞いた。
組織として存在感高める
ー日本の金型産業が抱える最大の課題とは。
時代が大きく変わろうとしている中で、その変化にどう対応するかが最大の課題だ。金型の需要の大半を占める自動車産業では電動化や自動化などによって100年に1度の変革期にあると言われ、既存の大手メーカーでも主導権をとれるとは限らない。新興メーカーの台頭によって今まで顧客だったところが変わる可能性も大いにあり得る。こうした変化を乗り越えるには、“チームジャパン”で世界と対峙しないといけない。
ーそのためには。
金型メーカーはもっと量産を意識するべきではないか。金型を量産の道具と捉えると、ユーザーのことを考えなければ本当の意味で良い金型はつくれない。一方で、ユーザーも新しい素材や形状を量産するとなれば、それに対応した金型が不可欠。川下から川上産業までが一体となり、今まで以上に強い協力関係を結ぶことで、競争力の高いものづくりができると考えている。
ー人材も課題と言われている。
やはり産業を維持、発展させていくには人が欠かせない。外部環境の変化に対応できても、人手不足によって産業が瓦解しかねない。当工業会としては、海外人材の活用事例の発信や、金型の広報用DVDを作成して学生や一般向けの広報活動を積極的に進めたい。
ー昨年は次世代のリーダーを育てるための「金型マスター認定制度」を立ち上げた。
これからの時代、今までのように腕が良いだけで良い人材とは言えなくなっている。特に中核を担っていく人材にはマーケティングやマネジメントといった能力が求められるし、海外の商習慣なども把握しておかないといけない。「金型マスター認定制度」は、今後も継続的にアカデミーを開催し、まずは昨年認定した71人をグレードアップさせていく。そして来年には第2回の募集をするつもりだ。
ーそのほかに取り組みたいことは。
地域の活動を重視したい。全国の集まりなので、今までの型種別の活動だけでは全ての会員が参加するには限界がある。すでに静岡の浜松部会や北陸部会、九州地区会などがあるので、今後は中国や四国地区などにも活動を広げたい。
ー業界団体として今後の方向性は。
会員が満足する活動を進めるのはもちろんだが、それだけではなく日本の全ての金型メーカーの代弁者として情報を発信していく。それには会員増強が不可欠。当工業会の組織率は全国の金型メーカー6535社(2015年工業統計)に対して、会員数は407社(8月現在)とまだ5%強だ。これを20~30%に引き上げることで、国や政府に対しても存在感を高めていきたい。
金型新聞 平成30年(2018年)8月10日号
関連記事
後藤社長に聞く 見どころと狙い 12年ぶりに日進工具が精密微細加工に特化したプライベートショー「NSTOOLプライベートショー2020精密・微細加工技術展」。小径エンドミルはもとより、微細加工機、治具、そして切削加工ユ…
自動車のシートや骨格部品などのプレス金型を手掛けるササヤマは金型の競争力を高めるため、金型づくりのDXとベトナム子会社のデータ製作力の強化に取り組む。デジタル技術で金型づくりを効率化し、ベトナム子会社を同社グループのデー…
ものづくりのお役に立ちたい 未来を拓く新技術 来場者の技術革新に貢献 JIMTOFで展示された工作機械や機器、ソフトなど金型や部品加工における最新技術を一堂に集めて披露するUMモールドフェア。今回は新型の5軸加工機や…
営業改革や自社ブランド開発 まつやま・ひろのぶ1980年生まれ、東京都出身。2004年立教大学卒業後、UFJ銀行(現三菱UFJ銀行)に入行し、営業、企画などを経験した。19年扶桑精工に入社、20年同社社長に就任し、現在に…