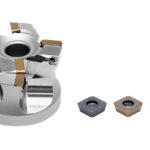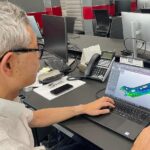ガイド〜位置決めをユニット化 ユーロテクノ(東京都杉並区、03-3391-1311)はこのほど、アガトン社(スイス)の射出成形金型用ローラーガイドピン「AGS」を発売した。ガイドから位置決めまでを一つのユニットで行うこと…
浜松工業技術支援センター SUS系粉末で金型造形
静岡県工業技術研究所浜松工業技術支援センター(浜松市浜名区)は、ステンレス系粉末を用いたプラスチック用金型の造形技術を開発した。これまで3Dプリンタでの造形が難しいとされていたSUS420J2系金型材料に相当する粉末で残留応力を低減する造形条件を確立。150㎜角を超える大型金型の造形を可能にした。プラスチック用金型における金属3Dプリンタの適用拡大が期待される。
残留応力低減、大型品に対応
造形に用いた材料は大同特殊鋼(名古屋市東区)のステンレス系粉末「LTX420」。2023年に販売開始した同材料は造形時に発生する歪みを大幅に低減し、造形品の割れを抑制することで、大型品の造形を可能とする。ただ、150㎜角を超える大型品での適用はまだ限定的で、凹凸のある複雑形状の造形条件は確立されていなかった。
浜松工業技術支援センターは独SLMソリューションズ社製の金属3Dプリンタ「SLM280」を用いて「LTX420」の造形技術の開発を進めた。特に造形品の割れの原因となる残留応力を低減する条件設定を研究。テストピースを造形し、ポータブル型Ⅹ線測定器で残留応力を測定しながら、レーザー出力や造形スピードなどを調整し、最適な造形条件を見出した。この条件によって、造形物の変位量を低減させ、相対密度は99・95%以上を実現した。

また、エネルギー密度と相対密度の関係を検証。レーザー出力が高いほど最適なエネルギー密度も高い傾向にあることを解明した。加えて、相対密度と内部欠陥サイズの関係も検証し、高密度化を図ることで欠陥サイズを100μm以下に抑えることができることも明らかにした。
テスト造形では幅185㎜×奥行160㎜×高さ84㎜の水管入り金型を製作。実際の金型を想定した複雑形状を組み入れ、造形時間は48時間30分だった。
今後はマシンニングセンタ(МC)による仕上げ加工や、水管内部の表面処理などの後工程を研究し、最終的な金型に仕上げる。また、完成した金型を使って成形し、性能評価や検証も行っていく予定。
「後工程でもノウハウが必要になる。例えば、造形品は55HRC程度と硬いため、そのままでは加工が難しい。熱処理を施すなどの工夫が必要。研究を重ね、知見を高めたい」(上席研究員の田光伸也氏)。
これまで金属3Dプリンタでの金型造形はマルエージング鋼相当の粉末が主流だった。しかし近年、金属3Dプリンタ用粉末の開発が進み、材料の選択肢が広がっている。ダイカスト用金型では熱間ダイス鋼「SKD61」相当の粉末が開発され、活用が進む。大型ダイカスト技術「ギガキャスト」向け金型などにも適用されている。
プラスチック用金型ではSUS420J2系金型材料に相当する粉末が開発されていたが、造形に時間がかかるなど実用化には課題が多かった。今後、浜松工業技術支援センターの研究によって、「LTX420」の造形技術が確立されれば、プラスチック用金型でもこれまで以上に金属3Dプリンタの活用が進む可能性が高い。
浜松工業技術支援センターは23年に「SLM280」1台を導入。静岡県内の企業向けに装置の利用を提供している。また、県内の企業や大学などを会員とした「静岡県積層造形技術(AM)協議会」を設立し、研究開発支援やセミナー開催などを行う。今回の開発もその一環。今後も金属3Dプリンタの活用促進や技術普及に向けた活動を進めていく考え。
金型新聞 2025年2月10日
関連記事
タングステン含有で焼付き防止 レーザー溶接機やメンテナンスなどを手掛けるALPHA LASER ENGINEERING(愛知県一宮市、0586・52・7133)は高温溶融アルミダイカスト用溶接棒「ALW」(TIG・レーザ…
高送りラジアスミル MOLDINO(東京都墨田区、03-6890-5101)はこのほど、アルファ高送りラジアスミル「TR4F形」のインサートサイズを拡大し、「TR4F5000形」を発売した。従来の12タイプから15タイプ…
新しい技術を活用して製造プロセスを効率化する、金型づくりのスマート化が広まっている。IoT(モノのインターネット)技術で機械の稼働状況を監視・分析したり、様々なサービスを提供したり、無人搬送車(AGV・AIV)でワーク…
スプリングバック、材料特性のばらつきに対応 ハイテン材加工に不可欠とされるCAE解析。すでに多くの金型メーカーが活用し、生産性や品質の向上につなげている。近年は自動車部材のハイテン化が進み、これまで以上に強度の高い超ハイ…