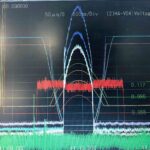成形技術の進化で変わる金型 構造部品など増える 電気自動車(EV)が金型づくりにも大きな影響を及ぼすことは間違いない。とりわけ、エンジンがなくなることでダイカスト型の減少を懸念する声も多い。元リョービで、日本ダイカスト…
【特集】日本の金型業界に必要な4つの課題 -デジタル化-
PART2 打田製作所 社長・打田尚道氏に聞く「デジタル化」

トップの判断が必要不可欠
業務フローを簡素化し、
現場が楽になること目指す
なぜ金型企業がデジタル化を進める必要があるか。ここでいうデジタル化を「人に依存していた情報や知識、ノウハウをデジタルデータ化すること」と定義した上で述べると、労働生産性を高め、競争力や付加価値、生活環境を向上させることが目的だと思います。
当社では2000年頃からデジタル化に取り組み始めました。それ以前から事務処理用パソコンをネットワークにつなぐといった取り組みは進めていたのですが、本格化したのは、インターネットが登場してからです。
取り組んだのはウェブシステムを活用したデータベースシステムを自社開発し、指示書や図面、部品発注など金型づくりに必要な情報を全て社内で共有できるようにしたことです。日々の引き合いや受注、生産状況などがリアルタイムで見られるため、紙で情報を管理していた時に比べ、格段に業務効率が向上しました。加えて、見積精度の向上や問い合わせへのレスポンスが良くなるなど顧客へのサービス向上にも効果がありました。
現在はさらに現場のデジタル化に取り組もうとしています。工作機械の稼働データを取得して効率的な設備運用を目指すためのシステム構築を検討し始めています。
約20年に渡ってこうした取り組みを進めてくると、デジタル活用における問題点もいくつか見えてきました。その一つが業務フローを変えずにデジタル化してしまうことです。デジタル化のために重複したデータ入力や、仕事のための仕事を作っていることがあるので、これらをまず整理し、業務フローを簡素化することが何よりも重要です。
もう一つが管理者目線でデジタル化してしまうこと。人は基本的に他人に拘束されたり、管理されたりすることを好みません。これを払拭するためには客観的にデジタル化の目的を説明することが必要です。あくまで現場担当者が楽になるデジタル化を目指すことが大切だと思います。
また、デジタルに依存してしまうことも問題点の一つだと感じます。デジタル化が進むと、「データに入っているから」とコミュニケーション不足に陥ることがあります。ただ、これではいけません。デジタル化はコミュニケーションをより早く、深く、正確にするためのものであり、主役はあくまで人だからです。
そして最後に挙げられるのは、やはり経営トップの決断・覚悟が必要ということです。過去にもOAやFA、CAD/CAMなどのトレンドがありましたが、これらは全て部分最適で済みました。しかし、今般のDXと表現されるデジタル化は、事業全体に関わるため、全業務フローで経営トップの判断が不可欠となります。また、対投資効果も見えにくく、数値にも表れにくいため、トップが将来の企業戦略を明示して取り組まないと、上手く成果につなげることはできないと思います。
デジタル化は特定のシステムを導入すれば解決するという道具論ではありません。自社の強みと弱み、外的な良い影響と悪い影響の分析はもちろん、社内にあふれるデータや情報を整理し、自社の見えざる資産や問題を見える化するという考えが必要だと思います。
金型新聞 2022年1月10日
関連記事
自動車の金型が試練の時を迎えている。半導体不足に端を発する新車開発の相次ぐ延期で受注が減少している。一方、電気自動車(EV)シフトが技術と産業構造に変革を迫る。生き残るカギは変化のうねりを見極め培ったノウハウや強みを生か…
新被膜やPCDでサブミクロン 仕上げや組付けなど金型の品質を決める領域には人の手は欠かせない。磨き工程もその一つ。しかし、磨きには時間や人手がかかることから、できるだけ機械加工で追い込み、磨きを減らしたいという声は多い。…
EV化などによる金型需要の変化やAMをはじめとする新たな製造技術の登場など金型産業を取り巻く環境はこれまで以上に大きく変化している。金型メーカーには今後も事業を継続、成長させていくため未来を見据えた取り組みが求められてい…
PART1:デジタル活用 精密金型の生産性を向上 トヨタ自動車が型造りで注力する取り組みの一つがデジタル活用だ。精密部品向けの金型を手掛けるモノづくりエンジニアリング部では、デジタルデータを活用することによって、金型だけ…