自動化と人材育成—。自動車産業に関わらず、あらゆる製造現場において共通の課題となっている。人手不足は深刻化しており、課題解消に自動化、省力化は欠かせない。いかに若手に技能を伝承していくかも喫緊の課題となっている。一方で、…
金型メーカー、自動車メーカーが図面データ標準化に向け語り合う【特集:図面データの標準化へ】
型技術者会議2025特別セッション1 で講演
金型のサプライチェーンには3次元や2次元、紙など様々な形式の図面が行き交っている。それが金型設計の時間、コスト、人材育成の手間がかかる原因になっている。サプライチェーン全体で図面データを標準化することはできないだろうか。自動車金型づくり効率化推進会議のメンバーが中心となり型技術者会議2025で語り合った。(講演と追加取材で講演内容をまとめた)
目次
- 大髙製作所・大髙晃洋社長「2Dと3Dのハイブリッド」
- デジタル標準企画・座間宏一代表「標準化の目的明確に」
- 岐阜精機工業・福山利治社長「ダイカストやプラも標準化すれば」
- トヨタ自動車モビリティツーリング部主査・荒井清志氏「金型3D図面の規格標準化へ」
- 日産自動車プレス技術部第二圧型製作課・廣渡清之氏「規格共通化6つのテーマ」
- 深江特殊鋼豊田技術センター長・難波浩氏「協力企業も3D化を」
- 経済産業省素形材産業室・星野昌志室長(当時)「DXの一丁目一番地」
- パネルディスカッション 図面3D化への課題について議論
大髙製作所・大髙晃洋社長「2Dと3Dのハイブリッド」

当社は、油・空圧機器や測定機器、半導体製造装置など様々な産業機器や装置の部品のダイカスト金型を手掛けています。以前までは、取引する鋳造メーカーから支給される2次元の製品図面がFAXで届くことがよくありました。
FAXだとそれをもとに3次元(3D)CADで図面を引き直さないといけない。アイソメ図があり、デジタルデータがあるのがわかっているのに、またCADデータを最初から入力するため手間がかかる。FAXで届くのは鋳造メーカーや中間の商社が3DCADを持っていないのが理由です。
今ではFAXを強制的に廃止し全受注件数の30%を3D図面で支給してもらっています。とはいえ支給データが文字化けなど不具合のあるケースもあるし、残りの70%はPDF図面なので設計には今なお多くの手間がかかっています。
金型は図面の3D化が進んでいます。しかし丸物の金型部品や板金金型は2Dの方が理解しやすいし、3Dを読めない人もいます。私見としては3Dと2Dの併用が今の金型づくりの実態にマッチすると思います。
例えば、3Dと2Dの機能を併せ持つCADがあれば便利と思います。図面を3Dにも2Dにもワンクリックで簡単に切り替えられる。そんなCADを開発することはできないかとソフトメーカーに相談しています。
新たな技術を導入し中国の金型メーカーが急激に力をつけてきているなかで、旧来のアナログの方法を続けている場合ではありません。図面設計に関わる業務を効率化し生産性を高めなければ、世界の競争から振り落とされてしまいます。
デジタル標準企画・座間宏一代表「標準化の目的明確に」

金型の設計図面の規格を標準化する。そのうえで最も大切なのは最終的な目的を明確にすることだと思います。当面の目的で規格づくりを進めていくと、必要以上の品質になったり、目的を果たせない内容になったりしてしまうことがあるからです。
例えば日本の自動車メーカーとボディ部品のプレス金型メーカーが図面設計のルールを決める。しかしこのルールは日本の自動車メーカーとボディ部品の金型メーカーの効率や品質が良くなることが目的でそれ例外のことを考慮していません。
そのためこのルールを海外でも適用しようと現地企業に呼び掛けても、受け入れられないことが考えられます。海外での適用も目的とするのなら、ISOが定める図面設計の思想や規格を取り入れる必要があります。
しかし、目指す目的が日本の自動車のボディ部品のプレス金型の図面設計における効率化と品質向であるなら、そんなことをする必要はありません。むしろ自動車のボディ部品の金型に関連する企業に最もメリットの出る規格を追求する方が良い。
つまるところ、設計図面の規格標準化による最終的な目的と、それによる参画企業へのメリットを明確にする。そのうえで規格づくりを進める方が、目指す規格が完成すると思うのです。
ただ、どのような規格を目指すにしても規格に関する様々な情報知ることが大切です。業界におけるローカルルールも国際基準もそれぞれに優れた点がある。それを理解したうえで取り入れることができれば、より良い規格になると思います。
岐阜精機工業・福山利治社長「ダイカストやプラも標準化すれば」
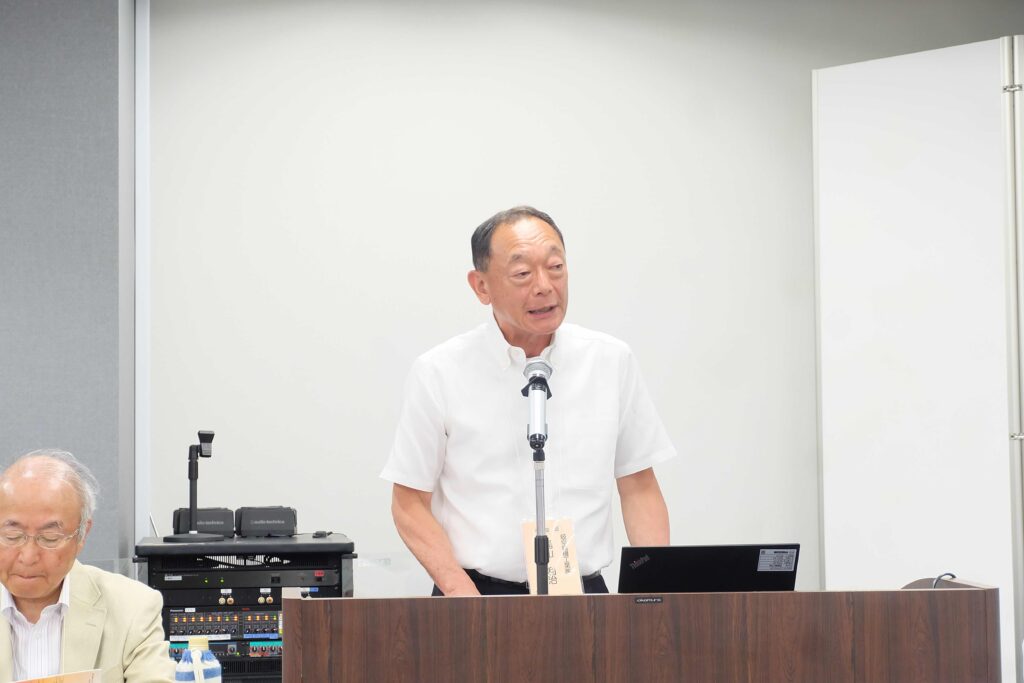
当社は自動車のバンパーなどのプラスチック金型やエンジン部品などのダイカスト金型を手掛けています。課題のひとつが、中国の金型メーカーとの価格における競争です。
資金力とマンパワーを強みとする中国企業に価格競争するのは難しい。そこで金型づくりを効率化しリードタイムの早さをストロングポイントにしたいと思っています。その方策のひとつが金型設計の効率化です。
ただ、ダイカスト金型は自動車メーカー各社が指定する公差に統一性がありません。固有のキャスティングの技術があり金型の仕様も異なります。その知識を理解し設計する必要があります。
加えて、鋳造温度が650℃前後になるダイカスト金型はメンテナンスが必要です。そのため金型を製作する際の3次元データとは別に、自動車メーカーが修理で用いる2次元図面も納めます。
プラスチック金型は設計にある程度自由度があります。成形した製品の品質が検収の対象となるので、当社独自のノウハウに基づくアイデアを図面に盛り込める。型設計に意志入れができます。
とはいえ、ダイカスト金型もプラスチック金型も、自動車メーカーに共通する加工属性の色分けや加工の公差や基準、型部品の名称はありません。これらが標準化されれば設計の効率はより向上すると思います。
自動車メーカー各社で異なる仕様や名称を覚える必要がなくなることで、設計者の育成期間も短縮できる。設計者を短期間で育成できれば当社に限らず、日本の金型産業の競争力アップにつながります。
トヨタ自動車モビリティツーリング部主査・荒井清志氏「金型3D図面の規格標準化へ」

当社をはじめ自動車メーカーや金型メーカー、部品加工メーカーなどプレス金型業界の14社で昨年、「自動車金型づくり効率化推進会議」を発足しました。自動車ボディ部品のプレス金型の3D設計図面の規格を標準化および金型製作の効率化することを目指し取り組んでいます。
規格標準化に取り組むのは3D設計図面に関する共通のルールが無いためで、例えば「加工属性の色分け」や「タップ・ノック穴の形状指示」、「構造部やノック穴ピッチの公差」、「加工する時の基準面」。これらは自動車各社がそれぞれ独自のルールで指示してきました。
そのため金型・部品加工メーカーはそれぞれのルールや過剰な要求品質に対応する必要があり、そのためのルール差の読み解きや品質確認の問い合わせなどの煩雑な作業をしなければなりませんでした。本来、品質、納期に集中する時間を各社ルール対応に時間をとられていました。
そこで標準化により、まず①各社各様のルールや過剰品質を見直し、共通化と最適化を図り、図面設計の効率化を向上させる。次に②業界全体に3次元設計・製作を浸透させ、3次元から2次元化への置き換えのようなムダな作業を無くし、金型・部品加工メーカーに付加価値の高い仕事に集中してもらえるようにする。さらに③金型設計を学びやすくし、高度なスキルへの成長と人材育成の短期化につなげていきたい。
それにより自動車プレス金型のサプライチェーン全体で図面設計の効率を高め、ムダややり直しを無くし、品質や納期などの課題に力を入れ、日本の金型の競争力向上に貢献したいと思っています。今はプレス金型だけですが将来、この取り組みをプラスチックやダイカストなどほかの金型にも広げていきたい。
日産自動車プレス技術部第二圧型製作課・廣渡清之氏「規格共通化6つのテーマ」

自動車のボディ部品の金型の3D図面の規格共通化について、「自動車金型づくり効率化推進会議」では様々な課題が浮き彫りになりました。ただ、その全てを一度に検証し課題解決に取り組むのは難しいので、優先するテーマを6つに絞りました。
その6つは、①加工属性の色分けの共通化、②タップやノック穴の形状指示の統一化、③加工基準の最適化、④溶接や表面処理などの製作指示方法の最適化、⑤構造部やノック穴ピッチの加工公差の共通化・最適化⑥型部品名称の共有化です。
このうち比較的合意が得やすい「加工属性の色分けの共通化」「タップやノック穴の形状指示の統一化」「加工基準の最適化」から進めています。加工の色は14に分類し、タップとノック穴の形状指示も統一しました。加工基準も基準面の条件は合意し詳細を詰めています。
残りの3つは合意形成に時間を要するため議論を重ねています。例えば、「溶接や表面処理などの製作指示方法の最適化」は図面に指示を注記する会社と注記しない会社があり、する会社に合わせると、しない会社は設計に工数が増えます。
「構造部やノック穴ピッチの加工公差の共通化・最適化」は、±20μmを→±10μmとするなど狭い公差を基準にすると、それに対応するために新たに加工機が必要になる場合があります。部位によって最適な公差を議論しています。
「型部品名称の共通化」は、共通の言葉を決めました。ただ、型部品の名称が金型部門を超えてそれ以外の部門の発注システムにまで紐づいていることが多く、名称共通化による影響が大きくなることが課題です。
深江特殊鋼豊田技術センター長・難波浩氏「協力企業も3D化を」

当社は1959年に鋼材商社として創業しましたが、切断や加工へと事業領域を広げ現在、全事業の約70%を金型部品を始めとする金属加工品計製作が占めています。主に骨格やシートなど自動車のインナー部品の金型を手掛けており、その金型部品は協力先の金型や部品メーカーにも製作してもらいます。
製作依頼における課題が金型づくりの経験が豊富ではなく3次元(3D)に対応経験がない部品メーカーへの図面の支給です。当社は金型の設計や加工における一貫した3D対応化を進めており、協力先にも3D図面を支給しています。しかし3Dに対応できない協力先にはそれができない。
その場合は3D図面をPDFのファイル形式に変換して支給しています。3DPDF図面は金型を展開できるし加工指示や公差などの情報を確認できる。3DCADを持っていなくても金型の部品をつくるために必要な情報を理解できます。そのため一つずつPDFに変換しています。
ただ、時代の流れは3D化。自動車メーカーは部品のサプライチェーン全体で効率化を図るため、図面や加工プログラムの3D対応化を推進しています。ですが3D図面を受けた当社がそれをPDFファイルや2D図面に変換して支給している。サプライチェーンにおける3D対応は途切れています。
日本の金型産業は中小規模の協力企業も含めたサプライチェーン全体で支えている。こうした協力企業が3D化に対応できるように業界全体で取り組んでいかないと、産業全体の国際競争力も高まらない。当社も今から25年前、思い切って3D対応へとシフトしました。中小の金型や部品メーカーも3DCAMを導入するなど3Dに対応できるように業界で力を合わせて取組むことが必要と感じます。
経済産業省素形材産業室・星野昌志室長(当時)「DXの一丁目一番地」

経済産業省は今年3月、12年ぶりに「素形材産業ビジョン」を策定し、「稼ぐ力」の強化を究極の目的としました。素形材産業の力を高め、日本のものづくりの拠点としての機能を維持・強化につなげていきたいと思います。
稼ぐ力を高めるために、2040年の目標として①需要先、②海外展開、③新技術の3つを挙げました。需要先は自動車産業を維持しつつ、航空機など高付加価値分野を3割から5割まで高めること。海外展開も海外比率を3割から5割にアップさせること。新技術では、金属積層造形市場におけるシェアを2割にしようと数値目標も掲げました。これを達成するために定期的にフォローアップを実施していきます。
目標達成のために7つの行動の変容も指摘しました。そのひとつが「DX・標準化」。素形材企業の価値向上につながるDXの推進や、サプライチェーンのデータ連携による新たな価値創出に取り組んでいくことを目指します。
自動車金型づくり効率化推進会議は経産省としても、それを象徴する一丁目一番地の活動だと認識しています。ここにお集まりの方々には、この3D化への取り組みを全国に広げて欲しい。ビジョンは作って終わりではありません。ここからがスタートです。業界やそれを超えてビジョンを達成することを願っています。
パネルディスカッション 図面3D化への課題について議論
講演者によるパネルディスカッションも開かれた。聴講者から寄せられた「図面の3次元(3D)化を進めるために現場の意識を変える方法は」、「図面の注記を減らせないか」などの質問について議論した。(敬称略、質問と議論の一部を抜粋)

現場の意識を変える 供給網で3Dの流通を
質問 「紙図面の方が使いやすい」と言う現場の意識を変えることができますか。
福山:当社は現場に紙の図面がほぼありません。3Dデータを見ながら作業に対応しています。それは作業に必要な情報が3Dデータに入っているからです。現場の方々には3D化で何が便利になるか理解して頂くことだと思います。
岡山:当社は現場で紙図面を見ることはほぼありません。3D化を始めた当初、「3Dモデルを確認するのに手間がかかる」という声がありました。しかし責任者が「紙をなくす」とトップダウンで判断しました。
大高:そうした現場の声はドラフターからCADに移行した時もあったのだと思います。しかし結局、CADに移行しました。環境が変われば、それに対応していくと思います。
質問:図面の注記を減らせませんか。
廣渡:まさに注記については議論をしていることろです。注記が多いと3D図面は「ハリネズミ状態」になってしまいます。見えづらいだけでなく読みこむ作業が増えてしまいます。協力先からも「注記を減らして欲しい」、「データと色だけで公差を分かるようにして欲しい」という声が多く、工夫が必要と思います。
質問:CAMの活用を広げるにはどうすればいいでしょうか。
大高:金型メーカーはほぼCAMを使っていると思います。使っていないのは部品メーカーではないでしょうか。ただ、CAMに限らず3D化を広げるには別の課題があると思います。というのも、大手企業の殆どは3Dで設計しているのに、取引の間に入る商社や部品メーカーが3DCADを持っていない。そのためアイソメ図のデータさえもらえないことがあります。3Dで設計するということだけでなく、サプライチェーン全体で3D図面を流通させることが必要だと感じます。
聴講者:3D化が進んでいる欧米でも設計部門だけ3D化していることが多く、製造現場やサプライヤーまでつながることは少ないです。この取り組みを進めることで日本のものづくりの良さをより強くできると思う。
型技術者会議2025の大澤晋一郎実行委員長(トヨタ自動車モビリティツーリング部部長)が議論を総括した。
大澤:データを出す側、受ける側でコミュニケ—ションのギャップがあります。これを埋めるために議論することが大事。ギャップを解消しないと付加価値の高い作業に人的リソースを回せません。今後はプレスだけでなく樹脂やダイカストにも広げていきたい。より良いものづくり、金型づくりを広げるために一緒に取り組みましょう。
司会・講演者
- マツダ 技術本部 ツーリング製作部 アシスタントマネージャー 岡山一洋氏
- 大髙製作所 代表取締役 大髙晃洋氏
- デジタル標準企画 代表 座間宏一氏
- 岐阜精機工業 代表取締役社長 福山利治氏
- 深江特殊鋼 豊田技術センター長 難波浩氏
- トヨタ自動車 モノづくり開発センター モビリティツーリング部 主査 荒井清志氏
- 日産自動車 車両生産技術開発本部 プレス技術部 第二圧型製作課 廣渡清之氏
- 経済産業省 製造産業局 素形材産業室 星野昌志室長(当時)
金型しんぶん2025年8月10日号
関連記事
金型づくりの世界では、自動化やAM、脱炭素向けなどの最新技術が数多く登場し続けている。その進化は止まることがなく、4年ぶりに開催されたJIMTOF2022でも多数の最新技術が披露され、注目を集めた。今年最後となる本特集で…
トライ後の改修減らし生産性アップ 自動車の骨格部品などのプレス金型を手掛ける南工は昨年、解析速度の速いプレスシミュレーションソフトを導入した。短期間で高精度の塑性変形予測を割り出し、設計品質を高め、トライ後の改修時間も短…
日本金型工業厚生年金基金(上田勝弘理事長、以下金型基金)が今秋に制度移行を進める狙いは、現制度で抱える課題を解決するとともに、退職金の年金化など福利厚生の持続可能な制度の構築にある。以降2号にわたり、今の大きな3つの課…
造形ワークの大型化 近年盛り上がりを見せるAM(アディティブマニュファクチュアリング)。ここ数年のJIMTOFやインターモールドでもAMに特化した特設展が併催されるなど、国内外での注目度が高まっており、高精度な積層造形を…












