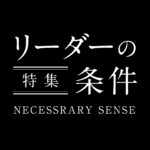協力企業との連携推進 時期によって業務の量に差が生じることは少なくない。特に金型業界では、製品のモデルチェンジや更新のタイミングなどに受注が集中するため、繁忙期と閑散期で現場の稼働状況は大きく異なる。繁忙期には残業や休日…
-混沌の時代を切り拓く- 金型メーカーの連携
金型広がる協力の輪
金型メーカー同士や異業種、加工技術などを軸とした様々な形での連携や協業の重要性が高まっている。ユーザーの海外展開に伴うサポートや需要開拓、技術の複合化や高度化などによって、金型メーカー単独では顧客の要望に応えきれないことが増えているためだ。こうした要望に応えるため、金型メーカー同士で連携したり、異業種でネットワークを構築したり、業界団体を立ち上げたりするなど、様々な形で連携が進んでいる。
海外対応や技術の高度化
タッグ組み対応の幅広げる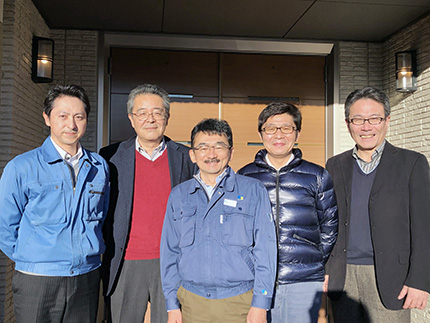
埼玉県の金型メーカーなど異業種5社でつくるチーム入間のメンバー。今年で発足から11年目を迎えた
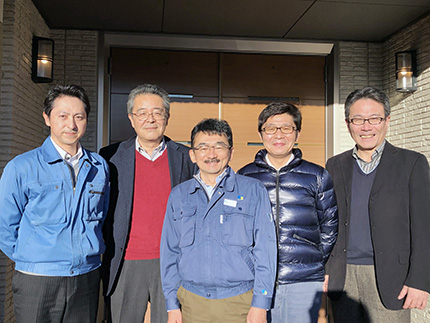
共同受注などの連携や協業はこれまでもあったが、その重要性が増している。人や設備など経営資本に限りのある金型メーカー単独では、対応しづらいことが増えていることが背景にある。
その一つが加速する市場のグローバル化だ。昨年の日系自動車メーカー8社の世界生産台数は2755万台。そのうち海外が1834万台なのだから、海外での金型需要はもとより、補修などの対応も増えるのは当然だ。
18年に業務提携した、プラスチック金型の伊勢金型工業と名古屋精密金型、ゴム型のエムエス製作所の3社もこの動きに対応する。相互の海外拠点を活用し、保守・メンテナンスで協力。グローバル化が進む顧客対応を最小投資で支援する。
海外の需要開拓も単独では難しい。企業間の連携ではないが、18年に発足した、金型メーカーも参画する「微細加工工業会」は、2月にアメリカで開かれる医療系の展示会に共同出展し、海外での需要開拓を目指す。
マルチマテリアル化に代表される技術の複合化や高度化への対応でも連携が重要になっている。アルミや樹脂、ハイテン材など複合的な知見が必要になることが多いからだ。ある鉄鋼メーカーの技術者は「どんなに優れた材料でも『使える』形にして初めて採用となる。他の材料や、接合、加工技術など、他分野の知見がより必要になっている」とし、加工メーカーと協業しているという。連携ではないが、三井化学による共和工業やアークのグループ化、東洋鋼鈑による富士テクニカ宮津の子会社化なども、素材から加工までといったこうした流れを反映しているのだろう。
樹脂や金属など複数の発注先をまとめたいという動きも増えている。管理コスト低減や品質の安定につながるからだ。
10年以上埼玉県の入間市周辺の加工受託集団「チーム入間」はまさにこの要求に対応する。プレス、プラスチック、ダイカストなどそれぞれ強みを持つ5社で、試作から量産を一括で請け負う提案をする。20年近い協業の歴史を持つ「京都試作ネット」も機械、金属、樹脂、ゴムなどの試作加工に特化したサービスを提供する。
日本金型工業会の学術顧問の横田悦二郎氏「金型は設備や人が制約条件になってしまうことが多い。日本の金型業界を一つの金型メーカーと捉えれば設備も人もそろっていてもっと色んな事ことができるはずだ」と連携の重要性を話している。
金型新聞 2020年2月10日
関連記事
日本金型工業厚生年金基金(上田勝弘理事長、以下金型基金)が今秋に制度移行を進める狙いは、現制度で抱える課題を解決するとともに、退職金の年金化など福利厚生の持続可能な制度の構築にある。以降2号にわたり、今の大きな3つの課…
サイベックコーポレーション 顧問 平林 健吾氏 1944年生まれ、長野県出身。工作機械メーカー、プレス部品メーカーを経て、73年に信友工業(現サイベックコーポレーション)を設立。2009年顧問。18年旭日単光章を受賞。…
製造業において、人手不足は深刻な問題となっている。困難な採用環境、熟練者の高齢化などに加え、働き方改革関連法の完全施行もあり、金型メーカー各社も対応に苦慮している。特に人手不足への対応は、生産性の向上はもとより、女性の…
金型産業 発展へ 日本金型工業会 5つの施策 出席者 エムエス製作所社長 迫田 幸博氏 小出製作所社長 小出 悟氏 長津製作所会長 牧野 俊清氏 日進精機相談役 加藤 忠郎氏 野田金型社長 堀口 展男氏 2月号で…