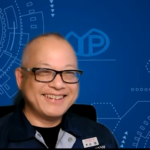今年5月、日本金型工業会東部支部の若手経営者が集う『天青会』の第52代会長に就いた。会員が減少傾向にある中、「もう一度“にぎわい”を取り戻したい」。卒業したOBにもイベントへの参加を呼びかけ、交流の輪を広げる考えだ。 埼…
情報収集や課題解決の場に 砥粒加工学会 会長インタビュー
今年3月、研削や研磨など砥粒加工技術の振興、発展を目的とした活動を行う砥粒加工学会の会長に就任した清水大介氏(牧野フライス精機社長)。金型メーカーに対して、「生産現場に直結した技術の発信を行う砥粒加工学会を情報収集や、加工課題について相談する場として、上手く使ってもらいたい」と話す。注力する取り組みや金型業界へのメッセージなどを聞いた。
金型とも連携し技術開発を

1977年生まれ。東京都出身。2000年慶應義塾大学商学部卒業、02年英国ノッティンガム大学大学院修了後、03年日本精工入社。08年 牧野フライス精機入社、社長に就任し、現在に至る。
砥粒加工学会とは。
砥粒加工に携わる技術者や研究者、学生など約900人、加工機や砥石メーカーなどの賛助会員約160社で構成される。会員には学会誌、セミナーや学術講演会への参加および発表、技術者に対する表彰などを提供している。
注力する取り組みは。
学会の第一義は、研究成果の発表や技術者・研究者の交流の場を提供すること。しかし、ここ数年はコロナ禍で多くの活動がオンラインとなっていた。今年度からは活動をリアルに戻し、活性化させていきたい。
そのためには。
会員を増強させることが課題だ。当学会は砥粒加工を中心に生産現場に直結した技術の発信を行っており、研究のシーズは生産現場にある。現場で技術課題を抱える金型メーカーを始めとした加工メーカーにもっと参加してもらうことで、新しい研究につながると考えている。
加工メーカーが参加するメリットは。
砥粒加工に関する最新の技術情報を得ることができる。特に仕上げ工程である研削や研磨などの砥粒加工は高い精度が求められる。なおさら常に最先端の情報が必要だと思う。困りごとを解決する情報収集の場として利用してほしい。
金型業界へのメッセージは。
金型はマザーツールであり、難削材や高硬度材など加工難度の高い加工材料が用いられるため、常に新しい加工原理を取り入れて、高い加工技術を有している業界だと考えている。特に近年は自動車の電動化などによって、新しい金型や材質の加工ニーズが増えている。当学会にはそれらの加工につながる技術を研究している技術者や研究者がいる。課題解決につながるはずだ。学会は敷居が高いというイメージがあると思うが、そんなことはない。どんどん参加してほしい。
砥粒加工の未来は。
いつの時代も最先端の加工技術は砥粒加工だった。硬いものを加工したり、表面を綺麗に加工したり。これからもそうだと考えている。現在、光学技術や解析技術などの進化によって、これまで難しかった砥粒の向きや配置などのコントロールも可能になりつつある。これが実用化されれば、さらなる技術革新が期待できる。砥粒加工技術は今後も発展の余地がある加工分野だ。
金型新聞 2023年6月10日
関連記事
当社は今年4月、同じ新潟県に拠点を構えるプラスチック金型メーカーの共和工業との協業を発表しました。主な目的は、電気自動車(EV)の車台やバッテリーケースなどを一体成形する「メガキャスト」向けの超大物金型の開発、製造です。…
新たに福岡工場が稼働 射出成形事業を強化 自動車向けプラスチック金型の設計・製作を手掛ける中村精工(岐阜県岐阜市、058-388-3551)は1月、成形事業及び金型メンテナンスを行う福岡工場(福岡県飯塚市)を立ち上げ、1…
コロナショックを機に、金型に求められること 5月12日、コロナウイルス拡大の影響が読めない中で、トヨタ自動車の豊田章男社長は「頼りにされ、必要とされる会社を目指し、世界中の仲間とともに強くなる」とのコメントを発表した。…
レーザー溶接・金型補修機器メーカーのテラスレーザー(静岡県駿河区)に入社したのは2年前。企業の販路開拓支援などに携わっていた前職時代、製造業とも多く関わる中で「世の中は製造業がなければ成立しないということを肌で感じ、自分…