産学官連携で共同研究 岐阜大学は6月7日、スマート金型開発拠点事業をスタートさせた。労働人口減少社会を想定し、より高効率な生産システムが求められる中、金型を使った量産システムでの不良率ゼロを可能にするスマート生産システ…
がんばれ!日本の金型産業特集
東洋ガラス機械 五味淵 忠 社長

東洋ガラス機械は東洋製罐グループの東洋ガラスの子会社で、ガラスびん用金型やプラスチックボトル用金型などを手掛けるメーカーだ。金型のほか、成形機械などの製造・販売もしており、「包装容器において、幅広い提案ができる技術力が強み」と五味淵忠社長は話す。
技術力とは、「顧客のあらゆる要求に対して応えられる」ことだ。プラスチック金型事業部長の足立伸雄氏は「ペットボトルの形状が複雑になってきているが、当社はどんな形状の金型でも製造できる」と強調する。それを実現するひとつが表面処理の内製化だ。凹凸が多い複雑な形状は離型性が悪く、サンドブラストなどで表面処理を施す必要があり、包装容器の金型には高い面品位が求められるため独自の技術やノウハウが必要となる。内製する高い表面処理技術を活かし、デザイン性の高い特殊な形状の金型製造に力を入れ、少量の成形品も製造するなど高付加価値化を図っている。
また、加工技術の機械化・自動化を進めている。ガラス金型事業部長の松尾秀則氏は「熟練工が減っているので、従来手作業で行っていた磨きなどをしなくていいように機械加工を行ない、製品のバラつきを無くしている」と話す。今春には、1チャッキングで全加工ができるAPC搭載の複合加工機を導入した。自動化を図り、生産性を向上することで、納期やコストに対して柔軟に対応ができる。技術や納期などあらゆる要求に応え、常に顧客の立場に立った金型づくりを目指している。
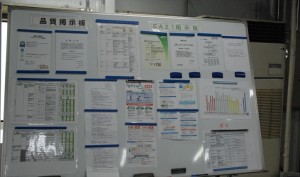
「多能工化し、自分で考えて行動できる人材を育成している」と話す五味淵社長。そうするのは、時代の流れからだ。五味淵社長は「同じものを作り続ける時代は終わり、今は多品種少ロット生産といわれるように、多種多様な製品づくりが求められている」。こうした製品づくりを実現するには、様々な機械を扱え、幅広い作業ができる人材が必要となる。ただ、多能工化をするには、「難しい時代になっているのも事実だ」という。多様化しすぎて、常に違う仕事を行い、ひとつひとつの工程を覚えきれずに別のステップに進み、なかなか技術やノウハウが身につかない。そうした問題があるからこそ、「基礎知識の充実」と「OJT」に力を入れる。「基礎知識の充実」では、例えば機械加工担当者に、位置決めの仕方はもちろん、その重要性など基礎的な知識から徹底して伝える。また、実務の中でノウハウや技術を習得させるために、ベテラン従業員とペアを組ませるなど「OJT」を積極的に取り入れ、根気強く育成を行う。
そのほか、会社全体が一つの方向性を持って仕事に取り組めるようにと、品質管理や環境活動などにも力を入れている。作業現場の掲示板に活動の目標や進捗状況を掲示し、従業員一人一人が常に取り組むべきことを意識させ、自分で考えて行動のできる人材を育成する。
こうした取り組みによって、多能工で自ら考え行動できる人材を育て、あらゆる要望に対して応えられる高いレベルの技術集団を目指していく。

代表者=代表取締役社長 五味淵忠氏
創立=1959年
所在地=神奈川県横浜市旭区川井本町76
TEL=045・953・8831
FAX=045・953・5137
URL=http://www.tgmm.co.jp/
資本金=1億円
従業員数=139人
事業内容=ガラス容器、プラスチック容器などの意匠設計、金型設計、金型製造販売。びん、プラスチック容器などの製造用機械の設計、製造販売など。
主な設備=NC旋盤25台、立型マシニングセンタ13台、高速マシニングセンタ11台、表面処理装置7台、複合旋盤6台、プラノミラー3台、NC放電加工機3台、NC横フライス2台、NC彫刻機2台、NC立フライス、ワイヤーカット各1台など。
金型新聞 平成26年(2014年)10月20日号
関連記事
アルミ、樹脂など軽量化の流れ加速 次世代型自動車の登場が金型業界に及ぼす影響を懸念する声は少なくない。「電気自動車(EV)でエンジンはどれほど減るのか」、「アルミや樹脂は増えるのか」などの疑問は尽きない。そこで本年の新…
コストダウン、納期短縮図る 自動車用アルミダイカスト部品メーカーの美濃工業(岐阜県中津川市、0573-66-1025)は2021年3月、埼玉県熊谷市に「熊谷金型センター」を設立し、金型製造を開始した。20年10月には静岡…
人材の定着を促進 岐阜県内の工業高校生を対象にした第3回工業高校生金型コンテストが12月8日、岐阜県立国際たくみアカデミー(岐阜県美濃加茂市)で開かれ、県内10校、関係者も含め約90人が参加した。 可児工業と高山工業が…
「設計の効率化は業務フロー全体を見直さないと意味がない」。そう話すのは、日本デザインエンジニアリングの岩壁清行社長。同氏は長年自身も金型づくりに携わり、近年ではフィリピンで設計支援を手掛ける。また、20年以上前から、日…














