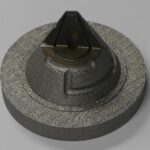パンチやダイ、強力ばねなどプレス金型部品を取り扱うオネストンは2021年に創業50周年を迎えた。プレス部品専門商社として基盤を築き、近年は「1個づくり」の特殊部品対応やリバースエンジニアリングほか、アメリカ・ケンタッキー…
日本金型工業会 学術顧問
横田 悦二郎 氏(日本工業大学客員教授)
〜鳥瞰蟻瞰〜

コロナを好機にするには営業など中間層の変革を
ICTの活用が絶対条件
ICTの活用が絶対条件
コロナで金型業界は難しい状況にありますが、大変だと騒いだり、パラダイムシフトを心配したりしても何も生まれません。むしろ、やり方次第では、ピンチをチャンスに変えることができるのではないかと考えています。それには冷静になって、変わるもの、変わらないものを考える必要があります。
まず、変わらないものは何でしょうか。コロナでも、金型を「作る」部分は変わりません。新技術が登場し、作り方は変化しますが、本質的に鉄を削って任意の形を「作る」ことは不変です。また、自動車や家電メーカーが製品を作ることも変わらないので、量産の道具として金型を必要とする構造は変わらないでしょう。
一方、変わるのは何でしょうか。人と人の接触が最も多い、金型づくりでは中間層にあたる営業や受注のあり方だと思います。すでにユーザーが訪問制限をかける中、リモートワークが浸透し、コミュニケーションの方法は変化しています。リモートが便利だと分かれば利用が増える可能性が高い。しかし、対応次第では金型メーカーにとってチャンスになるのではないかと思います。
まず、リモートワークが広がれば営業のための事務所を持つ必要がなくなる。リモートで対応できることが増えれば、訪問回数が減り、営業コストが減らせます。マンパワーに限りがある金型メーカーは助かるはずです。
もう一つはユーザーとの関係性です。つながることが常態化すれば、打ち合わせに技術者も加わりやすくなり、顧客との距離は近くなる可能性が高い。技術者同士が直接やり取りしたり、金型図面を見ながら「ああでもない」、「こうして欲しい」とリアルタイムで話をしたりできるかもしれない。伝言ゲームが多い金型づくりでは、技術者同士が会話できるメリットが大きいのは誰もが分かるはずです。
一方で、気を付けなければならないこともあります。距離や時間の障壁がなくなるので、ユーザーとの物理的な距離は強みではなくなります。簡単につながれるので、生産途中の報告が求められたり、納期が短くなったりするかもしれない。
いずれにしても、こうした変化に対応するには「ICT技術の活用」が絶対条件になります。ホームページのようなものではなく、リアルタイムで納期や生産プロセスなどの情報を発信したり、常に技術相談に応じたりできる、ウェブ上の営業所のような仕組みを構築することが必要になるかもしれません。
コロナは金型メーカーに変化を迫りますが、やり方次第でチャンスになりえます。ただ、これまでの延長線上で考えていてはダメです。従来型の金型経営は終焉を迎えたと思ったほうがいい。今までの常識を捨てるのではなく、いったん横に置いて考える必要があると思います。
金型新聞 2020年6月4日
関連記事
廃棄部分の再利用も可能に 高機能フィルムの製造に適した押出成形金型「Tダイ」などの設計を手掛けるアクスモールディング。同社は、今年の3月にソディックの金属3Dプリンター「LPM325S」を導入。押出成形金型の設計の簡易化…
業界の弱体化は顧客にマイナス ユーザーと金型メーカーはどちらかが欠けても成り立たない「イコールパートナー」だと訴えてきました。我々の事業を安定させるためにも、値上げは粘り強く要求していくべきで、そのためには足並みをそろえ…
プレス加工メーカーの新栄工業(千葉市花見川区、043-258-2310)は2019年末に、プレス金型メーカーのアポロ工業(埼玉県吉川市)を資本提携によってグループ化した。「M&Aは事業領域の拡大や技術の強化につなげるこ…
当社は創業から50年間、冷間圧造金型一本で事業を続けてきました。しかし、10年後も同じように事業を続けていられるかというと、そうは考えていません。今ある仕事は相当減っていると思います。感覚的な予測になりますが、だいたい3…