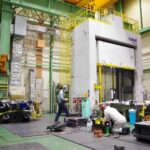研削力高いセラミック砥石 ALPHA LASER ENGINEERINGは昨年11月、独自ブランドの金型用セラミック砥石を発売した。優れた研削能力や耐熱性が特長で、広がる金型リユースの需要に応えていくという。市川社長に開…
情報収集や課題解決の場に 砥粒加工学会 会長インタビュー
今年3月、研削や研磨など砥粒加工技術の振興、発展を目的とした活動を行う砥粒加工学会の会長に就任した清水大介氏(牧野フライス精機社長)。金型メーカーに対して、「生産現場に直結した技術の発信を行う砥粒加工学会を情報収集や、加工課題について相談する場として、上手く使ってもらいたい」と話す。注力する取り組みや金型業界へのメッセージなどを聞いた。
金型とも連携し技術開発を

1977年生まれ。東京都出身。2000年慶應義塾大学商学部卒業、02年英国ノッティンガム大学大学院修了後、03年日本精工入社。08年 牧野フライス精機入社、社長に就任し、現在に至る。
砥粒加工学会とは。
砥粒加工に携わる技術者や研究者、学生など約900人、加工機や砥石メーカーなどの賛助会員約160社で構成される。会員には学会誌、セミナーや学術講演会への参加および発表、技術者に対する表彰などを提供している。
注力する取り組みは。
学会の第一義は、研究成果の発表や技術者・研究者の交流の場を提供すること。しかし、ここ数年はコロナ禍で多くの活動がオンラインとなっていた。今年度からは活動をリアルに戻し、活性化させていきたい。
そのためには。
会員を増強させることが課題だ。当学会は砥粒加工を中心に生産現場に直結した技術の発信を行っており、研究のシーズは生産現場にある。現場で技術課題を抱える金型メーカーを始めとした加工メーカーにもっと参加してもらうことで、新しい研究につながると考えている。
加工メーカーが参加するメリットは。
砥粒加工に関する最新の技術情報を得ることができる。特に仕上げ工程である研削や研磨などの砥粒加工は高い精度が求められる。なおさら常に最先端の情報が必要だと思う。困りごとを解決する情報収集の場として利用してほしい。
金型業界へのメッセージは。
金型はマザーツールであり、難削材や高硬度材など加工難度の高い加工材料が用いられるため、常に新しい加工原理を取り入れて、高い加工技術を有している業界だと考えている。特に近年は自動車の電動化などによって、新しい金型や材質の加工ニーズが増えている。当学会にはそれらの加工につながる技術を研究している技術者や研究者がいる。課題解決につながるはずだ。学会は敷居が高いというイメージがあると思うが、そんなことはない。どんどん参加してほしい。
砥粒加工の未来は。
いつの時代も最先端の加工技術は砥粒加工だった。硬いものを加工したり、表面を綺麗に加工したり。これからもそうだと考えている。現在、光学技術や解析技術などの進化によって、これまで難しかった砥粒の向きや配置などのコントロールも可能になりつつある。これが実用化されれば、さらなる技術革新が期待できる。砥粒加工技術は今後も発展の余地がある加工分野だ。
金型新聞 2023年6月10日
関連記事
粉末冶金金型メーカーの小林工業(秋田県由利本荘市)は、今年の6月に社長を交代。新社長として、佐藤正樹氏が就任した。佐藤社長に今の意気込みや注力していくこと、今後の目標などを聞いた。 ―これまでの経歴を教えてください 代表…
自動車のウェザーストリップなどゴム金型を手掛けるエムエス製作所(愛知県清須市)は人材育成に力を入れ、『現代の名工』や『あいちの名工』、国家検定資格の1級技能士を多数輩出している。2023年にNC旋盤工で『現代の名工』を受…
金型は成長産業 「金型は世界的には成長産業」―。そう話すのはCAD/CAMメーカー、C&Gシステムズの塩田聖一社長。コンピューターエンジニアリング(CE)とグラフィックプロダクツ(GP)の合併から4年半、年平均の成長率1…
ダイカスト金型を中心としたアルミニウム鋳造用金型専業メーカーのユニオン精機(兵庫県加古川市、079・425・0765)。型締力1000t以上の大物金型を得意とし、二輪・四輪車や汎用エンジンなどのアルミニウム鋳造部品に対応…