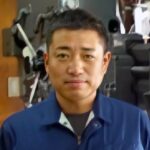超硬合金の素材や金型などを手掛ける冨士ダイス(東京都大田区、春田善和社長)が自動化・省人化に注力している。同社は2025年3月期から2027年3月期までの中期経営計画(中計)で「生産性向上・業務効率化」を掲げ、今期だけで…
大垣精工 代表取締役専務 松尾 幸雄氏「新しいことに挑戦することが技術の向上につながる」
経験による予測が不可欠
若い人は好奇心旺盛であれ
新しいことに挑戦して

日本の金型はますます難易度が高くなる一方、若手が基礎を学び、簡単なことから経験し、成長していく土壌が失われつつあります。だからこそ、過去の経験や技術を伝えることが重要です。
私が大学(工学部機械科)を卒業した頃はオイルショックの不景気で就職先も限られていました。だから、大学の教授から「大卒らしからぬ仕事を与えられるかもしれないが全力で取り組みなさい」と励まされたものです。縁があり、大垣精工に入社しましたが、金型のカの字も分かりませんでした。学校で習ったのは旋盤やフライス盤ぐらいでしたから。そこから仕上げ工として働き、先輩に教えてもらいながら技術習得に専念しました。好奇心は人一倍あり、名古屋の展示会に行き、放電加工機、ワイヤーカット、NC機が登場すると、導入している企業へ見学させてもらうなど率先して学びに行きました。
当時は単発プレス金型がメインで、順送金型といった難しい金型はまだ製作していませんでしたが、顧客から新しい仕事を受注していったことで、金型の構造や知識、ノウハウを習得できたと思います。私も現場から設計に移り、様々な型設計に挑みました。例えば、ブラウン管テレビの電子銃(電子ビームを生成する装置)の金型は独特な構造で、インターネットのない時代だから情報も少なく、見様見真似で作っては失敗の連続でした。ある時、金型の立ち上げで中国に行った際は検収が上がらず、再度日本へ持ち帰って修正し、中国へ戻るという経験もあります。大変でしたが、現地の金型メーカーからアドバイスを受けるなど、電子銃の金型で学んだことは今でも活きています。
これまで得てきた金型の知識や知恵、ノウハウは当社の技術遺産です。50年以上、何でも受けていくという姿勢でがむしゃらに金型を作ってきたからこそ、金型に対する知見やノウハウも広がったのだと思っています。プレス金型では専門メーカーや特定工法に強いなど固有技術を持つ企業が多く存在します。そうした独自技術を若手に伝えることが業界の課題です。
今の若い技術者、特に型設計者は大変です。昔は金型の基礎からスタートできたのが、一足飛びに高難易度な仕事から始めます。また、2D/3D図面、CAD/CAM操作、解析など覚えることも増え、昔のように現場に出て肌感覚を身に着けるような時間の余裕もありません。だからこそ、指導者の立場となった今、技術継承するために伝えなければいけないことを伝えています。若手からうっとおしいと思われても、過去の経験や金型について語っています。当社の育成法はOJTです。金型は一品一様の世界で、学校で覚えたことが役立つとは限らず、場数を踏んで多くの経験を積まないと分からないことも多い世界です。だから、若い技術者には『好奇心旺盛であれ』と言いたい。身の回りのモノがどのように作られているか興味を持ち、新しいことに挑戦することが技術の向上につながります。失敗することもあるでしょう。私も失敗を重ねましたが、これまで怒られた経験はありません。そうした若手の挑戦を後押しできる社風を作ることもベテランの役目と感じています。
金型新聞 2022年2月10日
関連記事
要望に合わせ創造と変革 「色々と教えると新しい経営はできないだろうから、あなたには多くは教えない」―。工作機械業界のカリスマ、牧野二郎前社長がそう伝えるほど、全幅の信頼を置く。 顧客重視をより進化 入社時に「機械もソ…
いかにトライ数を減らすか ―アルミ材用金型に取り組んだきっかけは。 「1988年にホンダのNSXに関わったのがきっかけ。オールアルミボディを採用した自動車で、当社では一部の金型を手掛け、量産はほぼ全てのアルミ部品の生産…
コロナを好機にするには 営業など中間層の変革をICTの活用が絶対条件 コロナで金型業界は難しい状況にありますが、大変だと騒いだり、パラダイムシフトを心配したりしても何も生まれません。むしろ、やり方次第では、ピンチをチャ…
一桁ミクロンの加工精度 「マシニングで出せない精度の穴加工は、是非任せてほしい」と語るのは、長年ジグボーラー加工やジグ研削加工に携わってきた、太陽テクニカの大畠正陽社長。同社は、航空・宇宙産業の部品から工作機械の主要精密…