デジタルマーケティングで見込客を獲得 近年は国内の金型市場が縮小しており、いかに新規開拓を行うかが大きな課題となっており、効率良く営業活動を展開するための仕組みやシステムの構築も求められる。年間の新規引き合い件数500件…
冨士ダイス、生産性向上へ自動化を推進 輪竹生産本部長「2030年までに30~40%省人化」
超硬合金の素材や金型などを手掛ける冨士ダイス(東京都大田区、春田善和社長)が自動化・省人化に注力している。同社は2025年3月期から2027年3月期までの中期経営計画(中計)で「生産性向上・業務効率化」を掲げ、今期だけでも自動化推進に1億6000万円を投資する。ロボットや複合加工機などを導入し、冶金の成形加工や超硬金型の荒加工などの自動化・省人化を推進する計画だ。今年1月に生産本部長、6月に取締役に就任した輪竹暢久氏に現場改革の方向性について聞いた。

―中計で「生産性向上・業務効率化」を掲げる理由を教えてください。
取締役生産本部長・輪竹暢久氏(以下、輪竹氏):効率改革は、前回の中計(2022年3月期~2024年3月期)から取り組んでいます。製造現場における“ムダ取り”を中心に取り組み、それなりに成果を上げました。現在の中計は、その維持、継続が柱の一つです。6S活動(整理、整頓、清掃、清潔、しつけ、セーフティ)は続けることが重要ですが、これが難しい。そこをしっかりと取り組みたいと考えています。
そして、もう一つの柱が自動化・省人化です。人材不足は今後さらに深刻化し、人材確保もますます困難になります。また、原材料費の高騰、労務費の上昇などに対応していくには、利益向上が必須となります。自動化・省人化はそのための手段の一つと考えています。
―具体的にどんな取り組みを進めているのでしょうか。
輪竹氏:昨年1年間は準備期間として、まずは冨士ダイスとしての自動化の将来像を描くことから始めました。自動化推進担当を設け、何を自動化し、自動化しないのかを明確化しました。現状、自動化できない工程は、金型の仕上げ。この工程はミクロンオーダーの精度が求められるので、機械任せにできるレベルではないと思います。
では、どこを自動化するか。私たちが考えるのは上工程です。当社は超硬合金から製造していますが、原料粉末をプレス成形した後の加工工程はそこまで公差が厳しくありません。この冶金の成形工程は積極的に自動化を進めていきます。粉末成形プレス機へのロボットアームの追加、成形加工機への自動搬送ロボットの導入などを予定しています。目指すのは無人化ですが、まずは2030年までに30~40%省人化したいと考えています。
また、金型加工の荒工程も自動化を進めます。公差は100分台で成形工程よりも厳しくはなりますが、自動化は可能だと思います。郡山製造所ではすでに円筒研削加工に自動化ロボットを導入し、生産性が10%向上しました。今期は複合加工機を導入し、段取り工程の削減などを計画しています。
その他にも、部品取りを最適化するCAD/CAMの自動ネスティングや、洗浄ロボットなどの導入も予定しています。今期は5~6件の自動化を進めています。
―自動化・省人化を実現した先にはどんなことが考えられますか。
輪竹氏:自動化・省人化によって創出された時間や人的余裕は、より付加価値の高い領域に充てたいと考えています。例えば、教育や学習、改善活動、研究開発、仕上げなどです。また、自動化・省人化は作業者の負荷を減らすこともできます。働きやすい環境を整備することで、人材の確保にもつながると考えています。
―どんな生産現場を目指しますか。
輪竹氏:主体性のある現場を目指したいと考えています。当社は長らくオーナー企業特有のトップダウン体制でした。そのため、示されたやるべきことに対して自ら行動する自主性は高いのですが、自ら考え、判断し、行動するという主体性を持つ人材は少ないと感じています。中計で掲げる「変化に対応できる企業体質への転換」にあるように、変化の激しい時代を生き抜くには、社員一人ひとりの主体性が重要となります。現在、主体性のある人材を発掘、育成するために、若手人材との交流を増やしたり、主体性を高めるための「コーチング」などに取り組んだりしています。
こうした取り組みはタイの現地法人で社長を務めていた経験が生きています。「タイ人は人につく」と言われるため、従業員とのコミュニケーションを何よりも重視し、従業員の話をよく聞き一緒に考えるということに多くの時間を費やしました。その甲斐あって、タイでは生産現場の改革を上手く進めることができ、生産性を2倍に引き上げることができました。
生産本部は会社の中でも大きな部隊で、会社の推進力にならないといけない。主体性のある人たちが積極的に活動、連携し、さらにその輪を広げていくことで、中計に掲げるような変化に対応できる企業体質へと転換できると考えています。
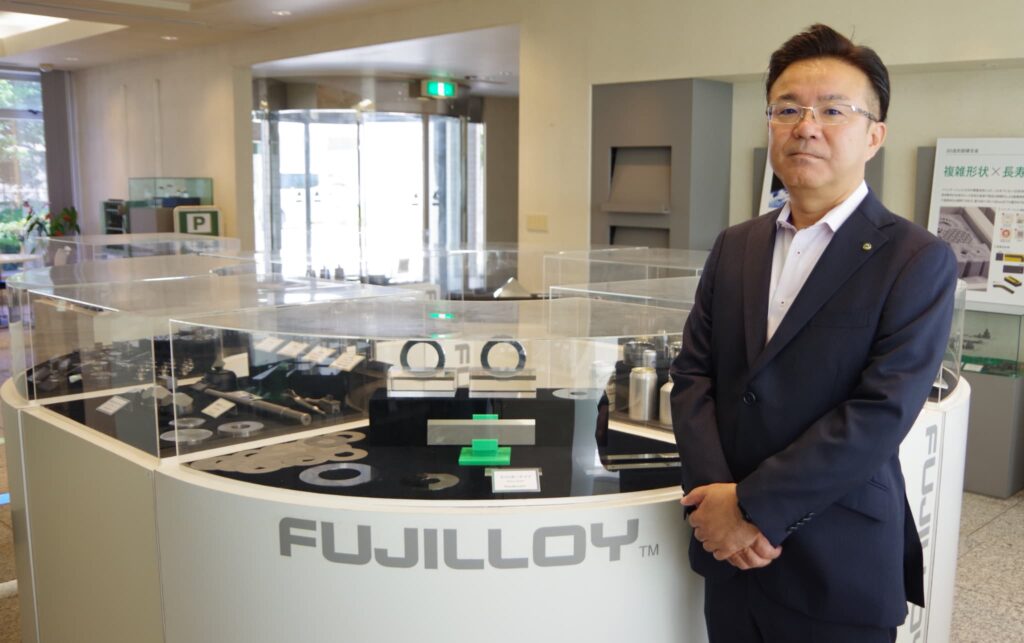
1970年生まれ、福岡県出身。1991年に冨士ダイス入社し、門司工場(2017年閉鎖)の製造課で20年間従事。その後、生産技術部を経て、2015年からタイ現地法人で社長を務めた。2023年に帰国し熊本製造所所長、2024年に生産副本部長と生産技術部を兼務し、現在に至る。
関連記事
コロナを好機にするには 営業など中間層の変革をICTの活用が絶対条件 コロナで金型業界は難しい状況にありますが、大変だと騒いだり、パラダイムシフトを心配したりしても何も生まれません。むしろ、やり方次第では、ピンチをチャ…
多台持ちで生産効率化 ジーシステムはプレス金型用プレートなどの研磨加工を手掛ける。車の電動化や5Gの広がりを背景に電子部品向けの需要が拡大している。於保信一郎社長は、「さらに効率化して生産性を高め、需要に応えていきたい」…
GFマシニングソリューションズ(横浜市神奈川区、045・450・1625)は今年8月、AM事業部長の小林貞人氏が社長に就任した。放電加工機やマシニングセンタ(MC)、自動化システムなどを手掛ける同社は今後、日本の金型業界…
三菱電機は50年以上に渡って、高精度、高性能な放電加工機を開発し、付加価値の高い金型づくりに貢献してきた。近年では省人化ニーズへの対応に注力する他、金属3Dプリンタを開発するなど技術領域を広げている。同社は今後、金型業界…












