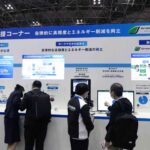自動車のシートや骨格部品などのプレス金型を手掛けるササヤマは金型の競争力を高めるため、金型づくりのDXとベトナム子会社のデータ製作力の強化に取り組む。デジタル技術で金型づくりを効率化し、ベトナム子会社を同社グループのデー…
ものつくり大学 西 直美教授に聞く
ダイカスト金型の未来
成形技術の進化で変わる金型
構造部品など増える
電気自動車(EV)が金型づくりにも大きな影響を及ぼすことは間違いない。とりわけ、エンジンがなくなることでダイカスト型の減少を懸念する声も多い。元リョービで、日本ダイカスト協会の技術部長を務めた、ものつくり大学の西直美教授にダイカスト製品や金型の将来を聞いた。
 ーEVでエンジンンの減少が懸念されている。
ーEVでエンジンンの減少が懸念されている。
「長期的には、エンジンやミッションなど大型のダイカスト品は減っていくだろう。一方、EVでもバッテリケースなどはなくならないし、ヒートシンクや構造部品などは増える可能性もある」。
「大型メーカーが小物に進出し競争が厳しくなることもあるだろう。さらに、樹脂、ハイテンなどマルチマテリアル化が進むので、他分野と競争も厳しくなる。ダイカストの優位性を保つ技術革新が必要だ」。
ー例えばどんなもの?
「鋳造品のガスを減らすことができる高真空ダイカストなども一つだ。型内を100ヘクトパスカル(大気圧の10分の1)以下の状態にすることで、鋳造後のガスを減らせ、薄肉成形も可能になり、熱処理や溶接ができるので、今後もっと増えていくと思う」。
ー金型も変わる?
「真空を維持するために、金型にOリングを埋め込んだり、押出ピンにもシールを張ったりするなどシール技術がより重要になると思う」。
ー構造部品などでもアルミ化の提案も増えている。
「薄肉化の一方、エンジンマウントやナックルなど構造部品の厚物などもアルミ化が期待されている分野だ。ここでは、低速で溶湯を充填する層流ダイカスト成形が増えている。厚物で熱量が多いため、長寿命の型が必要になるので、コーティングなど表面処理技術が重要な要素になる。同じ厚物向けでは、低圧鋳造とダイカストを組み合わせ、小さなマシンで大きな部品を成形できる方法なども出ていている」。
ー材料面での進化はいかがでしょうか。
「これも重要な視点だ。アルミとして使われているのは鋳造しやすいADC12が9割以上を占める。しかし靭性や延性が低いという欠点があり、自動車の重要保安部品には適用できない。そこで最近では、鉄の含有量を減らし、マンガンを添加した合金などが開発・実用化されており、自動車のサブフレームやアーム類などに採用されている。また、熱伝導率を高めたヒートシンクに適した材料なども開発されている。こうした素材の開発もチェックしておくべきだ」。
ー今後必要なことは。
「鋳造、材料両方の技術や知見が必要になる。マルチマテリアル化が進むなかで、金属積層造形の活用なども一部で進んでいるように、ダイカストの優位性を確保する技術革新を続けていくことが重要だ」。
金型新聞 平成29年(2017年)12月10日号
関連記事
金型づくりの世界では、自動化やAM、脱炭素向けなどの最新技術が数多く登場し続けている。その進化は止まることがなく、4年ぶりに開催されたJIMTOF2022でも多数の最新技術が披露され、注目を集めた。今年最後となる本特集で…
事業再構築補助金を活用 金型メーカーの新分野展開、業態転換が加速している。コロナ禍や、自動車の電動化などによって事業環境が大きく変化する金型業界。多くの金型メーカーが2021年からスタートした「事業再構築補助金」を活用し…
JIMTOF2022で次世代の技術としてひときわ注目を集めたのがデジタル技術だ。IoTやAI、クラウドなどを活用し機械の稼働状況監視や加工の不具合低減に生かす。金型づくりでもデジタルトランスフォーメーション(DX)が課題…
トヨタ自動車の豊田章男社長(現会長)が「自動車業界が百年に一度の変革期にある」と指摘して早5年。ここにきて、自動車メーカーの変化が加速してきた。トヨタは、大型アルミ部品を一体成形する「ギガキャスト」に参入すると発表。全個…