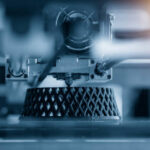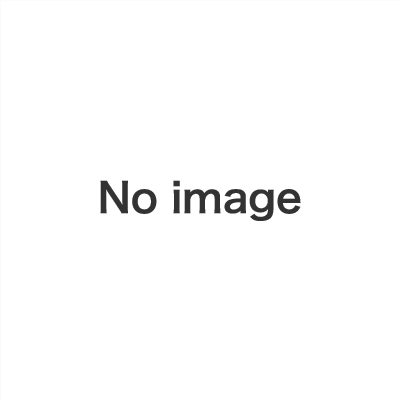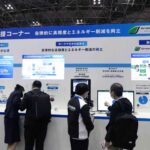金型メーカーの生産性向上が急務だ。少子高齢化による人手不足の深刻化に加え、金型メーカー事業所数の減少により1社当たりの生産負担が増加し、より多くの金型を生産できるかが金型メーカーの持続的成長の重要な要素の一つとなっている…
【鍛造金型特集】
日本鍛造協会 八木議廣会長に聞く
熱間鍛造の動向
鍛造は大きく熱間と冷間に分かれるが、重量ベースでは圧倒的に熱間が多い。成形品が比較的大きいことも理由の一つだ。一方で、金型はコストや納期の問題から圧倒的に内製率が高いという。自らも熱間鍛造部品を手掛ける、日本鍛造協会の八木議廣会長(八木工業社長)に熱間部品や熱間鍛造型の動向などを聞いた。
ー熱間部品では金型の調達はどうなっているのか。「当社は4割が内製で6割が外注だが、業界全体では9割が内製ではないか。基本内製という考えが主流だ」。
ーその理由は。
「熱間鍛造は素材をつぶす、成形、バリを取るなど複数の工程に分かれるが、成形工程の金型は、1回でダメになることもあり、納期面で外注では間に合わない。また、成形条件の設定が複雑で、金型にノウハウが詰め込まれており、競争力の面からも外には出せない。消耗品として金型を費用計上できるなど、コストメリットもある」。
ー日本の鍛造部品メーカーの競争力はどうか。
「納期やコスト、精度いずれでも競争力はあると思う。海外では自動車メーカーが鍛造を内製していないので、鍛造部品メーカーの力も強い。このため、価格は高い傾向にあり、特にコスト競争力は高い。そうした海外の需要を取り込むことが課題だ」。
ーそのほか課題は。
「熱や潤滑などのパラメータが多く、1200℃に熱した材料でも、成形条件は打つたびに代わる。そうした状況を安定させ、再現性を高めることも課題だろう。材料や電気代が高くなっているなか、安くつくることも重要になっている。二つの部品を一つにするなど一体成形したいという声は増えているほか、最近では一貫加工の要望も増えている」。
ー一貫加工とは。
「成形だけでなく、穴あけ、熱処理なども後工程も行うことだ。ユーザーも発注しやすく、管理しやすいからだ」。
ー市場の見通しは。
「熱間鍛造では約75%が自動車関連で、なかでも、足回り、クランクシャフトやコンロッドなどエンジン関連、トランスミッションなどの部品が多い。足元では、海外の自動車メーカーが日本国内の部品メーカーへの発注量が増えていて、忙しい。17年は05年以来の240万tを超えた。この水準は18年も続く」。
ーエンジンやミッションとなるとEV化への対応も必要ですね。
「長期的には部品点数の減少により、厳しくなり統廃合は必要になるかもしれない。とはいえ、そこは個々の企業で対応していくしかない」。
【関連記事:【鍛造金型特集】鍛造型、好調を持続 その背景や今後は】
金型新聞 平成30年(2018年)3月10日号
関連記事
新被膜やPCDでサブミクロン 仕上げや組付けなど金型の品質を決める領域には人の手は欠かせない。磨き工程もその一つ。しかし、磨きには時間や人手がかかることから、できるだけ機械加工で追い込み、磨きを減らしたいという声は多い。…
今回の“コロナ禍”で見えてきたのは、変化の必要性だ。受注や生産活動が制限される中、デデジタル化やITツールの活用など以前から指摘されていた課題が改めて浮き彫りになった。都内のある金型メーカーは、「変革の契機となるのは間違…
金型づくりの世界では、自動化やAM、脱炭素向けなどの最新技術が数多く登場し続けている。その進化は止まることがなく、4年ぶりに開催されたJIMTOF2022でも多数の最新技術が披露され、注目を集めた。今年最後となる本特集で…
自動車の電動化はダイカスト業界に大きな変化をもたらし始めている。バッテリーEVが増えるとエンジン関連の金型の減少は必至だ。一方で、バッテリーケースのアルミ化や、シャシーなどを一体造形する「メガキャスト」などで金型の大型化…