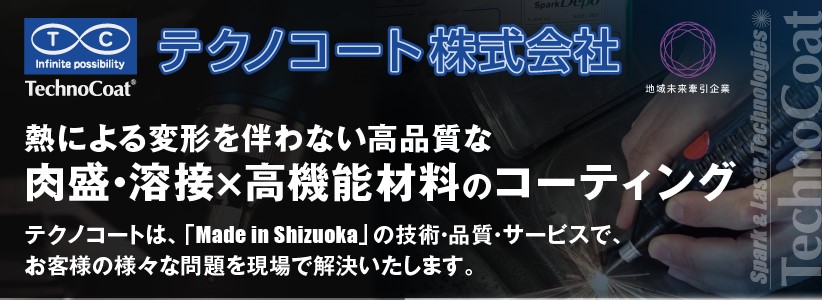この人に聞く 2018 電気自動車(EV)の登場で部品点数が減少したり、エンジンがなくなったりするのではないかといった金型への影響を危惧する声は絶えない。オートマチックトランスミッション(AT)や無段変速機(CVT)など…
AM技術の可能性
DMG森精機 AM部 ブルーメンシュテンゲル健太郎 部長に聞く

金属3Dプリンタを使った金属積層技術(AM技術)は様々な分野で広がっている。代表的なものは航空宇宙、医療、自動車で、さらに多方面へ拡大することは間違いない。そこで金属3Dプリンタを活用した次世代の金型づくりの可能性を探るべく、パウダーベッド方式の金属3Dプリンタとパウダーノズル方式と5軸加工機を組み合わせた複合加工機を販売するDMG森精機のAM部のブルーメンシュテンゲル健太郎部長に、金型における金属3Dプリンタの活用方法やメリット、将来性について聞いた。
冷却・補修・異種材の接合
2つの金属3Dプリンタの特長は。
AM技術は溶接に近く、パウダーベッド方式は一層ずつ積み上げる技術で、形状の自由度は高いが、造形速度は遅い。一方、パウダーノズル方式はベッド方式に比べ、形状の自由度は下がるものの、造形速度は速く、リードタイムが求められる分野に強い。当社はこの2つの技術と切削加工を併せ、ワンストップソリューションの総合力で金型分野に提案できる。
金型のメリットは。
金型における金属3Dプリンタのメリットは3つ。1つはベッド方式の形状の自由度を活かしたコンフォーマルクーリング(冷却水管)の製作で、成形面に合わせた自由な形状の冷却水管を作ることができる。もう1つは、ノズル方式と5軸加工による金型の補修だ。プレスや鍛造は摩耗が激しく、補修のリードタイム削減と品質の安定に課題を持っていた。従来の補修は溶接、焼入れ、熱処理など複数工程あり、それを1台の機械に集約すれば、人の技能による品質のばらつきがなく、リードタイムも最大80%削減した実績がある。AM技術を使うと、新品同様の高寿命に戻せた事例もある。最後は異種材の接合だ。例えば、プレスや鍛造の母材に焼入れ鋼を使用するが、そこに高速度工具鋼(ハイス鋼)を造形することでコーティングのような役割と同時に、マルテンサイトの効果で硬度も上がり、耐摩耗性に優れた金型にできる。
異種材の活用は広がっているのですか。
ドイツの金型研究者の間ではキャスティング2・0といって、異種材を組み合わせた金型の研究が活発になっている。キャスティングの課題は冷却で、穴加工だと強度に問題がでる。そこで、熱伝導率の高い銅合金を使い、金型の中に冷やしやすい金属の脈を作る。そうすれば、金型の割れの危険性も少なく、冷却性を高めることが可能だ。大手自動車メーカーでは、銅合金を付加し金型温度を260度から160度に下げることに成功した。新しい金型作りはすでに始まっている。
そのほかの活用は。
欧州自動車メーカーはホットプレスにAM技術を使う。例えば、冷却だ。業界テーマは耐摩耗性に優れた別材料を異種材の接合として使用できるかだ。そのほか、摩耗の激しい箇所に耐摩耗性に優れた材料を造形(コーティング)し、滑り、めくり上がりを防ぐことも考えている。
今後材料開発が加速
金型分野にAM技術を使う上で必要なことは。
金型設計だけでなく、金属3D造形も含めデザインを考える人材育成がポイント。また、材料の知識や金型を使用する中で、どこが摩耗しやすいかなど、金型の知見も重要になる。今は機械加工による仕上げが必要で、5軸のプログラミング知識も必要だ。
金属3Dプリンタの今後は。
科学や機械工学の進歩でAM技術に適した材料の開発が進むだろう。今の金属3Dプリンタ用の材料は他の用途で使っていた材料をAM技術に適合させたもの。3Dプリンタ独自の材料が開発されると、もっと大きなメリットが出てくる。AM技術は成長途中で、変化し続けている。技術も完成しておらず、我々もさらに具体化できるようにしたい。
金型新聞 2020年5月14日
関連記事
超精密金型部品や機能性金型部品、金型製作(プレス・モールド)を手掛ける新日本テックは設備や配管内に溜まった水垢(スケール)を除去する金型用水あか防止洗浄液を開発した。射出成形金型の温調水を流す配管のスケール除去などに有効…
自動車の電動化に商機 「日本に残る分野に経営資源を投下していく」。そう話すのは「エバーロイ」ブランドで知られる、超硬材料メーカーの共立合金製作所の池田伸也超硬事業部長。同社が国内で伸びると判断するのは、①大型の超硬材料…
令和元年に新社長に就任したオークマ・家城淳社長。市場が不透明化している中、「機電情知一体」「日本で作って世界で勝つ」を掲げるオークマの今後について家城社長の思いを聞いた。 家城淳社長愛知県出身。85年大隈鉄工所(現オ…
プレス金型やウレタン発泡成形金型を手掛ける黒田機型製作所は今年4月、事業再構築補助金を活用し、金属3Dプリンタを導入した。高い冷却効果が求められるバイオ樹脂向けの金型開発に着手する。主力の自動車業界に加え、新たな事業の柱…