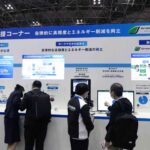デジタル技術の進化で、相次いで登場する新技術。次世代の匠はそれらの技術を金型づくりにどのように活かしているのか。また、それら能力を習得するには、どのようなスキルや育成が必要なのか。本特集では、様々ある新技術の中でも、次世…
【検証】変わる金型基金 新たな船出3
年金有期化で安定運用
前号では、日本金型工業厚生年金基金(上田勝弘理事長、以下金型基金)の現行制度の「定額加算」と「高い予定利率」の2つの課題とその解決策を紹介した。本号では、3つ目で最大の課題でもある「終身年金」の課題と、新制度ではどのように乗り越えていくのかをみていく。
【検証】変わる金型基金 新たな船出 解散後、新制度に移行
【検証】変わる金型基金 新たな船出2 3つの大きな課題解決へ
第一回目でも触れたように、金型年金は厚生年金基金の運用を一部代行してきた。こうした関係から、金型基金も死亡するまで支払い続ける「終身年金」を取らざるを得なかった。新たな制度では、給付期限がある「有期年金化」に変更する計画だ。
なぜ有期年金とする必要があるのか。最大の理由が長寿命化だ。2014年の日本の男性平均寿命は80.5歳で、基金発足時の69.18歳より10年以上も長くなっている。死亡時まで払い続ける終身年金だと、当然ながら長寿命化が進むほど給付額は増え続ける。
実際に17年3月時点での金型基金の平均受給期間18年9カ月。それに対して、現在は年金原資を15年で分割支払いしている。つまり、足りなくなる給付額は掛金の増加や、運用益を高めるなどして、補填する必要がある。このように終身制度を維持するとなると、財務上の負担が増すことから、「企業年金では有期が主流」(荒木健太郎常務理事)だという。
つまり、制度移行に伴い、有期年金化することで、基金の財務負担を減らすのが狙いだ。その代わり、終身というメリットはなくなるものの、事業者の負担も現行制度と変わらず運用できるわけだ。ただ、新制度では受給者の経済状況や要望に合わせ、有期の年金支給期間を5、10、15、20年の4つから選べるようにする予定だ。
2回にわたり「定額加算」、「高い予定利率」、「終身年金」の3つの課題と新制度移行による解決策をみてきたが、そもそもいったん解散し制度を移行するスキームを取るのはなぜなのか。その最大の理由は、代行返上だけして制度をそのまま引き継げば制約も多く、こうした大胆な施策や制度設計が描きづらいからだ。
次号以降では、基金を退職金化するなどの経営上の具体的なメリットや運用方法などを紹介する。
金型新聞 平成30年(2018年)3月10日号
関連記事
自動化と人材育成—。自動車産業に関わらず、あらゆる製造現場において共通の課題となっている。人手不足は深刻化しており、課題解消に自動化、省力化は欠かせない。いかに若手に技能を伝承していくかも喫緊の課題となっている。一方で、…
型青会を金型発注の窓口に 新春座談会ー第1部ー金型メーカー4社が語る 新時代の経営戦略 1月号では昨年の景況や各社の取り組みなどを報告してもらった。本号では日本金型工業会西部支部の青年部である「型青会」にスポットをあて…
金型づくりの世界では、自動化やAM、脱炭素向けなどの最新技術が数多く登場し続けている。その進化は止まることがなく、4年ぶりに開催されたJIMTOF2022でも多数の最新技術が披露され、注目を集めた。今年最後となる本特集で…
新被膜やPCDでサブミクロン 仕上げや組付けなど金型の品質を決める領域には人の手は欠かせない。磨き工程もその一つ。しかし、磨きには時間や人手がかかることから、できるだけ機械加工で追い込み、磨きを減らしたいという声は多い。…