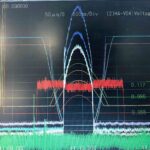PART1:デジタル活用 精密金型の生産性を向上 トヨタ自動車が型造りで注力する取り組みの一つがデジタル活用だ。精密部品向けの金型を手掛けるモノづくりエンジニアリング部では、デジタルデータを活用することによって、金型だけ…
微細加工でブランド化 稲垣哲也氏(アイジーエヴァース社長)【特集:次の10年を勝ち残る4つの道】
EV化などによる金型需要の変化やAMをはじめとする新たな製造技術の登場など金型産業を取り巻く環境はこれまで以上に大きく変化している。金型メーカーには今後も事業を継続、成長させていくため未来を見据えた取り組みが求められている。既存の事業を強化するのか、派生技術を伸ばすのか、あるいは新事業に手を伸ばすのか。さまざまな戦略が考えられる。金型メーカー経営者にインタビューし、次の10年を勝ち残るための戦略について聞いた。
派生技術を伸ばす
自動車部品向けの鍛造、プレス、樹脂など様々な金型製作を行うアイジーエヴァースは近年、微細加工技術の強化を進め、切削加工ドリームコンテスト2022(DMG森精機主催)で金賞を受賞するなど高精度・高難度な加工に挑戦している。

今後需要が高まるEV部品は高精度化が求められる。微細加工なくして高精度、高難度なものは作れないと考え、設備投資や技術開発を進めたのがきっかけ。微細加工はアートにも近く、企業のブランディングにつながるといった強みもある。
微細加工の要求精度を実現するには、恒温工場の空調完備、微細CAM及び機械オペレータのスキル向上、機械・工具・加工条件のデータベース化が重要で、トライ&エラーを繰り返し、加工技術を進化させる必要がある。直近、多数の展示会にも出展し、少しずつ微細加工の試作や車以外の市場からも依頼が増えてきた。
将来、金型の需要は減少傾向と思われる。その中で生き残っていくには現在の柱である金型製作、EV部品試作加工に加え、新しい市場の開拓も必要。それには他社にない価値を創らなければならない。
今年4月、新本社工場が完成し、微細加工も含め、新たな価値の創造を進める。それは5軸加工による微細加工(±2~3μm)の実現に加え、材質やサイズの異なる多品種なワークを自動で加工できるシステムの構築を検討している。日本のものづくりが世界に勝るには『超短納期』で顧客に対応すること。先が読めないからこそ、時流が動いた時にいち早く対応できる体制を整えておくことが最善と捉えている。
他の特集記事は以下から
- 金型経営者アンケート 次の10年を勝ち残るために取り組むこととは?【特集:次の10年を勝ち残る4つの道】
- 金型製作の効率化を追求 笹山勝氏(ササヤマ社長)【金型を強化する】
- 低廉化金型を開発 魚岸成光氏(魚岸精機工業社長)【金型を強化する】
- メンテナンスに革命を 清水一蔵氏(福井精機工業社長)【成形へと拡大する】
- ガラス両面MLAを量産 三重野計滋氏(ワークス社長)【成形へと拡大する】
- 自ら商品を生み出す道に 山添重幸氏(かいわ社長)【自社商品を創る】
- BtoC向け開拓に力 浦竹重行氏(東亜成型社長)【自社商品を創る】
金型新聞 2023年1月10日
関連記事
事業再構築補助金を活用 金型メーカーの新分野展開、業態転換が加速している。コロナ禍や、自動車の電動化などによって事業環境が大きく変化する金型業界。多くの金型メーカーが2021年からスタートした「事業再構築補助金」を活用し…
JIMTOF2022で注目を集めたテーマの一つが、カーボンニュートラルや環境対応だ。工作機械メーカーを始め、多くの出展企業がCO2排出量の削減や環境負荷低減につながる製品や技術を紹介した。世界的にカーボンニュートラルが求…
自動車の電動化や軽量化ニーズの高まり、短納期化、熟練作業者の減少など、プレス加工を取り巻く環境は大きく変化している。プレス加工メーカーへの要求も高度化しており、これまで以上に技術革新を進め、変化するニーズに対応することが…
培った技術活かす 自動車の電動化、医療関連や半導体関連需要の拡大などで、国内のものづくり産業に求められるものも大きく変化している。自動車の電動化ではモータやバッテリーなどの電動化部品や材料置換による軽量化部品などが増えて…